
日本の食料自給率
気候変動と食
年々気候変動で日本の食ものんびりと構える事ができなくなってきてるようです。
日本の食を支えている地域が大雨などにより収穫が不可になってしまうと物価上昇
そして各家庭に食べ物が行き渡らなくなってしまうそんな事を考えてしまいます。

日本の食料自給率
日本の食料自給率は、2021年度で約4割です。
これは、1961年度の30.2%から徐々に上昇してきましたが
1990年度以降は低下傾向にあります。
食料自給率が低下している主な原因は、以下の通りです。
- 人口増加に伴う食料需要の増加
- 農業従事者の減少
- 農地の減少
- 気候変動による農業生産の不安定化
日本の食料自給率を向上させるためには、農業従事者の増加や農地の拡大、気候変動への対応などが必要です。
また、食料自給率を向上させる方法は
国民一人ひとりが食料の安全性や重要性を認識し、食品ロスを無くすことです。
日本の食料自給率は低いです。
なので日本は世界有数の食料輸入国なのです。
日本の食料安全保障と、第一次産業を守る為にも食料自給率を向上させることが重要です。
自給率の高い地域
日本の食料自給率が高い地域は、以下の通りです。
- 北海道
- 東北地方
- 九州地方
これらの地域は、広大な農地と豊かな水資源に恵まれているため、食料自給率が高い傾向にあります。
また、これらの地域では、農業技術が進歩しており、効率的な農業が行われています。
一方、食料自給率が低い地域は、以下の通りです。
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
これらの地域は、人口密度が高く、農地が少ないため、食料自給率が低い傾向にあります。
また、これらの地域では、農業技術が進歩していないため、効率的な農業が行われていません。
日本の食料自給率は、1961年度の30.2%から徐々に上昇してきましたが、1990年度以降は低下傾向にあります。
この原因は、人口増加に伴う食料需要の増加、農業従事者の減少、農地の減少、気候変動による農業生産の不安定化などが挙げられます。
食料自給率を向上させるためには、以下の取り組みが必要です。
- 農地の拡大
- 農業技術の向上
- 食料の消費量の削減
- 食料の輸入先の多様化
広大な平野と豊かな水資源
日本の食料自給率生産は、北海道が1位で、秋田県は2位です。
秋田県の食料自給率は、2021年度で約56%です。
秋田県は、北東北地方に位置し、広大な平野と豊かな水資源に恵まれています。
また、秋田県は、米、麦、大豆、野菜、果物、畜産物など、様々な農産物を生産しています。

秋田県の食料自給率が高い理由は、以下のとおりです。
- 広大な農地
- 豊かな水資源
- 適度な気候
- 農業技術の進歩
秋田県の気候は、農業に適した温帯から亜寒帯にかけての多様な気候帯が分布しています。
以下に、秋田県で生産される主要な農産物とその生産量をご紹介します。
- 米:約130万トン
- 麦:約20万トン
- 大豆:約3万トン
- 野菜:約100万トン
- 果物:約10万トン
- 畜産物:約10万トン
秋田県は、日本の台所、様々な農産物を生産しており、日本の食料自給率を支えくれております。
日本の食料を支える
秋田県は、日本の食料を支える重要な地域です。
米、麦、大豆、野菜、果物、畜産物など、様々な農産物を生産しています。
生産される農産物は、その品質の高さで知られており、日本各地で愛されています。
秋田県は、日本の食料自給率を支える重要な地域です。秋田県の農業は、日本の食料安全保障を守るためにも、重要な役割を果たしています。
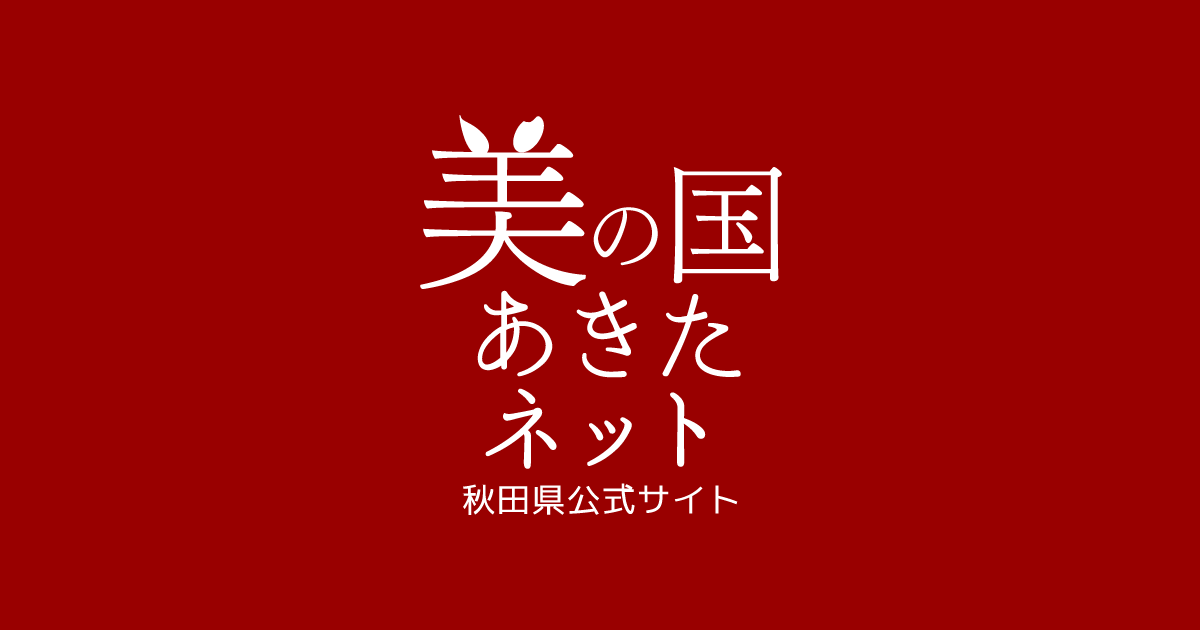
この度の大雨洪水により被災された皆様、ならびにそのご家族の皆様に心よりお見舞い申し上げます。 皆様の安全と被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。 被災された皆様の生活が1日も早く平穏に復することをお祈り申し上げます。





